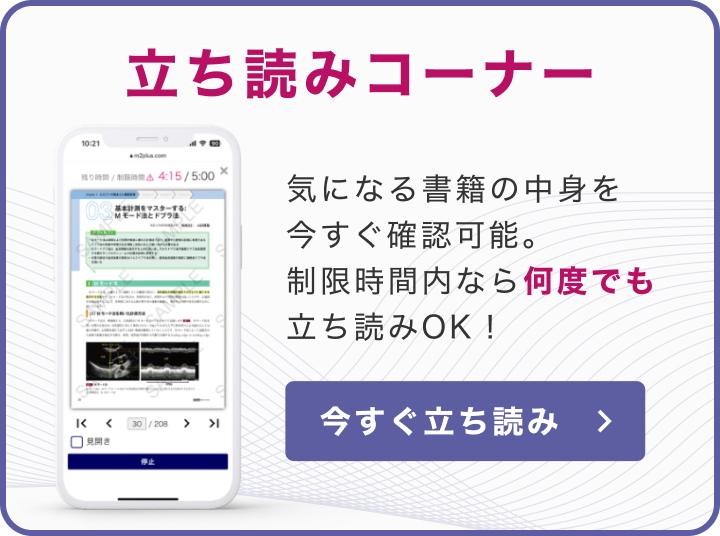- m3.com 電子書籍
- 基礎から学ぶ微生物学
商品情報
内容
微生物の分類から代謝,遺伝子工学,物質生産までを体系的に学べる初学者向けのカラーテキスト.理農工学部や教養の微生物学で必須の内容をこの1冊に凝縮.貴重なアーキアの画像を含む約50点の微生物画像を掲載!
序文
序
「微生物学」は,高校では「生物」のなかに紛れていたことと思います.「生物は暗記科目だった.微生物学も同じでしょう!」と思っている人も多いと想像します.ですが,「微生物学」も「生物学」も,決して暗記科目ではありません.それぞれの最先端では,仮説検証型,あるいは博物学型の研究が進んでいて,新たな知見が積み上げられたり,これまでの学知が改訂されたりしています.両方とも,暗記科目から想像されるような,すでに出来上がった学問からはかけ離れたところにあります.
「いろいろなものを眼に見えるようにしたい!」という人類の好奇心から微生物学ははじまりました.微生物が見えるようになると,どのような種類のものがいるのか,という素朴な疑問が湧いてきます.そして数多くの微生物が知られるようになると,一般微生物学が幕を開けることになります.「今見えている微生物は,どのような働きをしているのだろうか?」という疑問からは,応用微生物学や微生物生態学がはじまったと考えることができますし,「この微生物はどのような遺伝情報をもっているのだろうか?」という疑問からは,ゲノム微生物学のはじまりを垣間見ることができます.
人類は疑問をもち続けます.新たな疑問には当然新しい答えが返ってくるでしょう.一方で,すでに答えのある疑問であっても,これまでとは別の角度で答えた場合には新たな展開が見えることもあり,それはたいへん興味深いことです.ただし,答えのある疑問に対してこれまでと同じ角度で答えを出しても,これまでの答えと同じものとなるのは必然です.ここに,学問を系統立てて学ぶ必然性や必要性があると,私は考えます.
学ぶためには重要な歴史的な事実を正しく理解する必要があります.問題を解決するために先人はどのように考え行動したのでしょうか.皆さんが新たな課題に向かう時の一助になって欲しいという思いから,先人の愚直なまでの努力や,エレガントな方法による研究を皆さんにお見せしていきたいと思います.
私たちの身の回りには微生物が溢れています.基本眼に見えないことが理由で,学ぶのが後回しになってきた「微生物学」ですが,体系的に学ぶとおもしろさに気づけるだけでなく,「生物学」の奥深さを再認識できるようになるでしょう.
本書は,理農工系学部の初年次や,教養として学ぶ学生の皆さんを対象にして執筆しましたが,それより上の学年の皆さんの参考書としてもきっと役に立つことと思います.
微生物学をどうぞ楽しんでください.
2025年6月
石井正治
目次
1章 微生物学のオーバービュー
1-1 微生物の遍在性
1-2 微生物学の成立
1-3 微生物学とは
1-4 多岐にわたる微生物学
1)一般微生物学 2)応用微生物学 3)病原微生物学 4)極限環境微生物学 5)微生物生態学 6)ゲノム微生物学 7)食品微生物学
1-5 微生物学の未来像
1)単離微生物を基盤とする微生物学 2)微生物叢を対象とする微生物学 3)微生物ゲノムを基盤とする微生物学 4)他の学問分野との連携
1-6 次章に向けて
章末問題
2章 微生物学の歴史
2-1 不可視物
2-2 微生物の可視化
2-3 微生物は微生物から
2-4 微生物の単離
2-5 微生物の多様性
2-6 次章に向けて
章末問題
3章 微生物の分類
3-1 分類の必要性
3-2 分類指標
1)微生物の形態・構造の観察による分類:物理的性質 2)生理学的性質による分類 3)生化学的性質による分類:化学分類 4)遺伝学的性質による分類:16S/18S rRNA遺伝子解析による分類
3-3 微生物分類の全体像
3-4 次章に向けて
章末問題
4章 微生物の種類と特徴
4-1 分類上の階級について
4-2 ドメインにおける分類
4-3 バクテリア
1)Aquificota門 2)Atribacterota門 3)Bdellovibrionota門 4)Campylobacterota門 5)Chlorobiota門 6)Chrysiogenota門 7)Cyanobacteriota門 8)Deinococcota門 9)Thermodesulfobacteriota門 10)Myxococcota門 11)Planctomycetota門 12)Pseudomonadota門 13)Thermotogota門 14)Actinomycetota門 15)Bacillota門 16)Mycoplasmaota門
4-4 アーキア
4-5 真核微生物
1)カビ,キノコ,酵母 2)カビ,キノコ,酵母の分類 3)真核藻類
4-6 バクテリオファージ
4-7 次章に向けて
章末問題
5章 微生物の栄養と増殖
5-1 炭素源とエネルギー源
5-2 窒素源,硫黄源,無機塩類と補因子
1)窒素源 2)硫黄源 3)無機塩類と補因子
5-3 微生物の増殖
1)増殖にかかわる因子 2)増殖特性 3)増殖測定法 4)増殖曲線 5)培養工学
5-4 独立栄養微生物がつかさどる代謝(独立栄養的二酸化炭素固定経路)
5-5 次章に向けて
章末問題
6章 微生物の遺伝学と遺伝子工学
6-1 微生物の分子生物学と遺伝学
1)遺伝子とDNA 2)DNA の二重らせん構造 3)DNA の複製 4)遺伝情報の発現 5)RNA 6)転写 7)タンパク質 8)翻訳
6-2 遺伝子発現制御
1)原核生物の遺伝子発現調節機構 2)真核生物の遺伝子発現調節機構
6-3 変異と修復
1)変異 2)修復 3)相同組換え
6-4 遺伝子工学とバイオテクノロジー
1)宿主ベクター系と遺伝子クローニング 2)PCR 法 3)塩基配列決定法 4)ゲノム編集技術 5)バイオテクノロジーへの応用
6-5 次章に向けて
章末問題
7章 微生物の代謝① ―代謝の基本と基質レベルのリン酸化―
7-1 代謝とは
7-2 代謝を駆動する物質(1):生体由来タンパク質(酵素)
7-3 酵素反応速度論
7-4 代謝を駆動する物質(2):生体エネルギー物質,生体由来酸化還元物質
1)生体エネルギー物質 2)生体由来酸化還元物質
7-5 第一のエネルギー獲得機構(基質レベルのリン酸化)
1)解糖系 2)ペントースリン酸経路 3)エントナー・ドゥドロフ経路 4)ヘテロ乳酸発酵経路 5)ビフィズム経路 6)プロピオン酸経路 7)アセトン・ブタノール発酵経路 8)アルギニンデイミナーゼ経路
7-6 生成した還元型物質をどのように酸化型に戻すか
7-7 次章に向けて
章末問題
8章 微生物の代謝② ―プロトン駆動力を利用したATP合成―
8-1 第二のエネルギー獲得機構(プロトン[H+]駆動力を利用したATP合成)
8-2 H+駆動力を生成する代謝
1)呼吸鎖電子伝達系 2)硝酸呼吸 3)硫酸呼吸 4)アンモニア酸化微生物のエネルギー代謝 5)亜硝酸酸化微生物のエネルギー代謝 6)水素細菌のエネルギー代謝 7)硫黄酸化微生物のエネルギー代謝 8)鉄酸化微生物のエネルギー代謝 9)アナモックス細菌のエネルギー代謝 10)脱炭酸を伴うエネルギー代謝 11)メタン生成微生物のエネルギー代謝 12)光合成細菌による代謝(光合成細菌にラン藻を含めない)
8-3 クエン酸サイクル(異化代謝の中心的サイクル)
8-4 次章に向けて
章末問題
9章 微生物の代謝③ ―生体関連化合物の生合成にかかわる代謝・補充反応―
9-1 生体関連化合物の生合成にかかわる代謝
1)糖新生 2)アミノ酸生合成 3)脂質生合成 4)核酸生合成
9-2 補充反応(アナプレロティック反応)
9-3 次章に向けて
章末問題
10章 微生物の代謝④ ―物質生産―
10-1 微生物の産業利用の概要:DBTLサイクルの重要性
10-2 単一微生物による物質生産
1)アミノ酸生産 2)タンパク質や酵素の生産 3)抗生物質の生産
10-3 微生物叢による物質生産
1)日本酒醸造(伝統的発酵食品①) 2)黒酢醸造(伝統的発酵食品②)
10-4 次章に向けて
章末問題
11章 微生物の生態と元素循環
11-1 微生物の存在と代謝
11-2 微生物間の相互作用
1)同じ微生物間の相互作用 2)異なる微生物間の相互作用
11-3 地球規模での元素循環における微生物の役割
1)水素 2)炭素 3)窒素 4)硫黄 5)リン
11-4 次章に向けて
章末問題
12章 微生物の取り扱い
12-1 滅菌と無菌操作
1)滅菌および殺菌・除菌技術 2)無菌操作
12-2 微生物の培養
1)培地 2)抗生物質 3)培養 4)細胞の回収(集菌) 5)微生物の単離
12-3 微生物の保存
1)継代培養保存法 2)凍結保存法 3)凍結乾燥保存法
12-4 本書のまとめ
章末問題
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:10.8MB以上(インストール時:30.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:43.3MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:10.8MB以上(インストール時:30.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:43.3MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784758121798
- ページ数:229頁
- 書籍発行日:2025年7月
- 電子版発売日:2025年8月5日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍アプリが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。