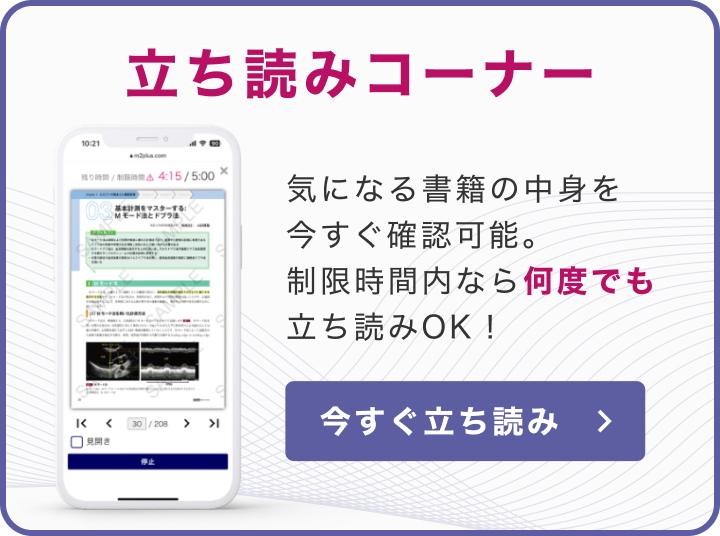- m3.com 電子書籍
- 言語聴覚士テキスト 第4版
商品情報
内容
●言語聴覚士に必要な障害学にかかわる領域を網羅し,重要かつ必要不可欠な知識・情報を,各分野の第一人者がわかりやすく解説.
●新たな知見・情報を取り入れて全体的に見直した定評あるテキストの改訂版.
●言語聴覚士学校養成所指定規則で新規科目として設定された「地域言語聴覚療法学」「言語聴覚療法管理学」の章を新設.
序文
第4版の序
コミュニケーション医学は,音声機能,言語機能,聴覚機能に支障をきたし生活の質が低下した患者さんを治療することを目標としています.これらの機能の維持・向上を図るために,検査や助言,指導,訓練を行う者として,わが国では1999年に国家資格をもつ言語聴覚士が誕生しました.今年で26年目となり,有資格者数は41,000 人を上回っています.これまで言語,聴覚,発声発語,摂食嚥下,高次脳機能などにかかわる医療に貢献してきましたが,2018年からは平衡機能検査が新たに業務に加わり,眼振電図検査と重心動揺計検査を実施できるようになりました.
病院やリハビリテーション施設などの医療機関での言語・嚥下訓練,特別支援学校や療育センターなどの教育機関での小児支援,デイサービスや老人保健施設などの介護施設でのリハビリテーション,訪問リハビリテーションや地域包括ケアシステムでの地域活動など,言語聴覚士はチーム医療の一員として幅広く活躍しています.2022年の診療報酬改定で,言語聴覚士の人数に関する条件が柔軟になったこともあり,補聴器や小児難聴,音声障害,摂食嚥下障害などに対応する専門的なリハビリテーションを提供する診療所も増えてきています.高齢者に多い誤嚥性肺炎や誤飲など嚥下機能に関するニーズが高いことに加え,2017年,2020年,2024年のLancet の報告で難聴が認知症の大きなリスク因子であることが明らかになり,社会的に言語や聴覚への関心が高まっています.
本書は2005年に第1版,2011年に第2版,2018年に第3版を刊行し,言語聴覚士の教育や育成に大きな役割を果たしてきました.医療機器や医薬品は急速に進化しており,リハビリテーション手技も進歩し,診療ガイドラインも更新されています.今回新しい執筆者にも加わっていただき,『言語聴覚士国家試験出題基準 令和5年4月版』をもとに言語聴覚士を目指す学生に必要な項目を記載し,2024年4月の言語聴覚士学校養成所指定規則の改正に伴い「地域言語聴覚療法学」「言語聴覚療法管理学」の章を新設するなど,全面的に見直しました.
執筆者には最新の医療に対応し,言語聴覚士の卒後の生涯教育や臨床現場で役立つ内容を意識して執筆していただき,第4版が上梓される運びとなりました.改めて感謝申し上げます.
本書がコミュニケーションを中心とした言語聴覚学の基本的な学習に役立ち,最新の情報にも対応し,リハビリテーション医療の質の向上に貢献することを願っています.
2024年12月
編者を代表して
大森孝一
目次
I 人体のしくみ・疾病と治療
1.医学総論(岡島康友)
1 健康・疾病・障害と社会環境
1.健康の概念
2.生活機能と障害
3.リハビリテーションとQOL
4.ノーマライゼーションとインクルージョン
2 医療倫理
1.医の倫理と臨床倫理
2.生命倫理と研究倫理
3.インフォームド・コンセント
4.専門職倫理と守秘義務
5.個人情報保護
3 医療行為
1.診療補助行為
2.チーム医療・多職種連携
3.地域医療・介護連携と地域包括ケア
4.医療安全
5.根拠に基づく医療
4 人口・保健統計
1.人口統計
2.疾病,死亡,介護の統計
5 疫学
1.疫学と臨床研究
2.臨床検査と感度・特異度
6 健康管理と予防医学
1.疾病の予防と早期発見
2.生活習慣病
7 母子保健
8 成人・老人保健
9 精神保健
10 感染症対策
1.院内感染
2.感染症予防,標準予防策
11 環境保健
2.解剖学・生理学(小林 靖)
1 人体の構成
1.人体の階層性
2.細胞
3.組織
4.器官と器官系
5.身体の部位や方向を表す用語
2 運動器系
1.骨格
2.骨格筋
3 循環器系
1.心臓
2.血管系
3.リンパ系
4 免疫系と血液
1.免疫細胞
2.リンパ節
3.胸腺
4.脾臓
5.血液
5 呼吸器系
1.鼻腔・副鼻腔
2.咽頭
3.喉頭
4.気管
5.肺
6.呼吸運動
6 消化器系
1.口腔
2.咽頭・食道
3.胃
4.小腸
5.大腸
6.蠕動運動
7.肝臓・胆嚢
8.膵臓
7 泌尿器系
1.腎臓
2.尿管
3.膀胱
4.尿道
8 生殖器系
1.男性生殖器
2.女性生殖器
9 内分泌系
1.視床下部・下垂体
2.松果体
3.甲状腺
4.副甲状腺(上皮小体)
5.副腎
6.性腺・胎盤
7.膵島(ランゲルハンス島)
8.消化管ホルモン
9.その他のホルモン
10 神経系
1.神経系の区分
2.神経系の細胞とその機能
3.中枢神経系
4.末梢神経系
5.自律神経系
11 感覚系
1.皮膚感覚
2.視覚
3.聴覚・平衡感覚
4.嗅覚・味覚
12 言語に関する器官の発生
3.病理学(小杉伊三夫)
1 疾病の原因
1.外因
2.内因
2 病変
1.退行性病変
2.進行性病変
3.循環障害
4.炎症
5.腫瘍
6.先天異常と奇形
3 遺伝
4 免疫
1.免疫過敏症による組織傷害とアレルギー疾患
2.自己免疫疾患
4.内科学(上月正博)
1 内科診断学総論
1.呼吸機能検査
2.循環機能検査
3.血液検査
4.尿検査
5.画像検査
2 内科治療学総論
1.急性疾患の管理
2.慢性疾患の管理
3 循環器疾患
1.先天性心疾患
2.心臓弁膜症
3.虚血性心疾患
4.高血圧と動脈硬化
5.心不全と不整脈
4 呼吸器疾患
1.上気道疾患
2.気管・気管支疾患
3.肺疾患
5 膠原病・アレルギー・免疫疾患
1.アレルギー疾患
2.気管支喘息
3.自己免疫疾患
4.膠原病
5.免疫不全
6 血液疾患
1.貧血
2.白血病
3.出血性疾患
7 消化器疾患
1.食道・胃・腸疾患
2.肝・胆道・膵疾患
8 腎臓疾患
1.腎炎・腎臓障害
2.腎不全
3.慢性腎臓病(CKD)
9 内分泌・代謝疾患
1.内分泌疾患
2.代謝疾患
10 感染症
1.感染症
2.感染症の予防と治療
11 老年病学
1.老年障害の特徴と疫学
2.老化
3.長期臥床
4.廃用症候群
5.サルコペニア・フレイル
6.栄養障害(低栄養)
5.小児科学(今高城治,加納優治)
1 小児科学とは
2 小児の成長と発達
1.発育区分
2.小児の成長
3.小児の発達
4.小児の栄養
5.被虐待児症候群
3 出生前医学・先天異常
1.先天異常
2.遺伝性疾患
3.多因子疾患
4.外的要因による先天異常
5.先天奇形
4 周産期医学
1.周産期障害
2.早産児,低出生体重児
3.出産時障害,新生児仮死
4.胎児発育不全
5.高ビリルビン血症,核黄疸
5 脳性麻痺と運動器疾患
1.脳性麻痺
2.脊髄性筋萎縮症
3.筋疾患
6 てんかんと痙攣性疾患
1.てんかん
2.その他の痙攣性疾患
7 中枢神経疾患
1.水頭症
2.変性
3.脳腫瘍
4.頭部外傷
8 感染症
1.小児感染症
2.中枢神経感染症
3.学校感染症
4.予防接種
9 神経発達症,発達障害
10 その他の疾患
1.循環器疾患
2.呼吸器疾患
3.消化器疾患
4.内分泌・代謝疾患
5.膠原病,アレルギー疾患
6.血液・造血器疾患,悪性新生物
7.腎・泌尿器疾患
8.精神疾患(心身症含む)
11 小児保健
6.精神医学(三村 將)
1 精神疾患の分類
1.内因性-心因性-器質性
2.操作的診断分類
2 正常と異常
1.正常性の判断
2.パーソナリティ障害
3.精神科症候学
3 内因性疾患
1.統合失調症
2.気分障害(感情障害)
4 心因性疾患
1.神経症
2.心因反応
3.心身症
4.生理的障害
5 器質性疾患
1.認知症(dementia)
2.中毒性精神障害
6 各年齢期の障害の特徴
7 精神保健
7.リハビリテーション医学(芳賀信彦)
1 概論
2 評価と検査
3 治療
4 疾患・障害のリハビリテーション
1.脳損傷
2.末梢神経障害
3.脳性麻痺
4.神経筋疾患
5.脊髄障害
6.骨・関節疾患
7.内部障害,悪性腫瘍
8.耳鼻咽喉科学(折舘伸彦)
A.耳科学
1 聴器の構造
1.外耳
2.鼓膜
3.中耳
4.内耳
5.聴覚路と聴中枢
2 聴覚系の機能
1.集音機構
2.伝音機構
3.感音機構
4.中枢聴覚路
5.両耳聴と方向覚
3 聴器の検査
4 難聴
5 外耳疾患
1.外耳道炎
2.先天性外耳道閉鎖症
6 中耳疾患
1.急性中耳炎
2.慢性中耳炎
3.真珠腫性中耳炎
4.滲出性中耳炎
5.耳硬化症
6.耳管開放症
7 内耳疾患
1.突発性難聴
2.外リンパ瘻
3.騒音性難聴
4.加齢性(老人性)難聴
5.内耳炎
6.遺伝性難聴
8 顔面神経疾患
1.ベル麻痺
2.ハント症候群
3.顔面痙攣
9 聴力改善手術
10 人工聴覚器の手術
11 前庭・平衡系の構造と機能
12 前庭・平衡系の検査
13 めまい疾患
1.メニエール病
2.良性発作性頭位めまい症
3.前庭神経炎
4.聴神経腫瘍
5.薬物中毒
B.鼻科学
1 固有鼻腔と副鼻腔の構造
2 固有鼻腔と副鼻腔の機能
3 固有鼻腔と副鼻腔の検査
4 鼻・副鼻腔疾患
1.急性鼻炎
2.慢性鼻炎
3.鼻アレルギー
4.急性副鼻腔炎
5.慢性副鼻腔炎
6.後鼻孔閉鎖症
5 嗅覚とその障害
C.口腔・咽頭科学
1 口腔・咽頭の構造
2 口腔・咽頭の機能
3 口腔・咽頭の検査
4 口腔疾患
1.舌炎
2.口内炎
3.口腔・舌腫瘍
4.唇裂
5.口蓋裂
5 咽頭疾患
1.急性扁桃炎
2.習慣性扁桃炎
3.慢性扁桃炎
4.扁桃肥大
5.アデノイド増殖症
6.睡眠時無呼吸症候群
7.咽頭腫瘍
6 唾液腺疾患
1.急性耳下腺炎
2.ムンプス(流行性耳下腺炎)
3.唾石症
7 鼻咽腔閉鎖不全をきたす疾患
8 味覚とその障害
D.喉頭科学
1 喉頭の構造
1.喉頭
2.声帯
2 喉頭の機能
1.呼気調節
2.発声(喉頭調節)
3.声道調節
4.声の年齢変化,変声
3 喉頭機能検査
4 喉頭疾患
1.急性喉頭炎
2.急性喉頭蓋炎
3.慢性喉頭炎
4.声帯ポリープ
5.ポリープ様声帯
6.声帯結節
7.声帯溝症
8.喉頭麻痺(声帯麻痺)
9.喉頭乳頭腫
10.喉頭癌
5 音声外科
6 喉頭摘出術
E.気管食道科学
1 気管・気管支・食道の構造
2 気管・気管支・食道の機能
3 気管・気管支・食道の検査
4 気管・気管支疾患
1.気管カニューレ抜去困難症
2.気管狭窄
5 食道疾患
6 気管切開と気道確保
7 嚥下障害
8 気道・食道異物
1.気道異物
2.食道異物
9.臨床神経学(永井知代子)
1 神経系の解剖・生理
1.中枢神経系の構造と機能
2.末梢神経系の構造と機能
3.伝導路
4.脳血管
5.髄液循環
2 神経学的検査
1.電気生理学的検査
2.画像検査
3 神経症候学(神経学的診察)
1.意識
2.脳神経系
3.運動系
4.感覚系
5.反射
6.髄膜刺激症候
4 臨床神経学各論
1.脳血管障害
2.頭部外傷(外傷性脳損傷)
3.脳腫瘍
4.中枢神経系感染症
5.神経変性疾患
6.認知症
7.水頭症
8.脱髄疾患
9.末梢神経障害
10.筋疾患(ミオパチー)および神経筋接合部疾患
11.代謝性疾患
12.その他の疾患
10.形成外科学(上田晃一)
1 形成外科総論
1.皮膚の解剖と生理
2.創傷治癒
2 組織移植
1.植皮
2.皮弁
3 外傷,熱傷,皮膚潰瘍
1.顔面外傷
2.顔面神経麻痺
3.顔面熱傷
4.気道熱傷
5.電撃傷,化学熱傷(損傷),凍傷,褥瘡
4 口唇・顎・口蓋裂
1.分類,発生
2.手術時期,術式
3.二次手術
4.口蓋裂に伴う合併症
5 頭蓋,顔面の先天異常
1.ピエール・ロバン(Pierre-Robin)症候群
2.トリーチャー・コリンズ(Treacher-Collins)症候群
3.頭蓋骨縫合早期癒合症
4.顔面裂
6 頭頸部手術に伴う障害
1.術後性障害
2.再建手術
7 瘢痕とケロイド
1.定義と臨床経過
2.肥厚性瘢痕とケロイドの相違
3.瘢痕拘縮
11.臨床歯科医学
A.臨床歯科医学(中原 貴)
1 歯・歯周組織
1.発生と構造
2.機能
3.疾患
4.治療
2 口腔,顎,顔面
1.発生と構造
2.機能
3 顎関節
1.発生と構造
2.機能
4 唾液腺
1.発生と構造
2.機能
5 口腔健康管理
1.予防
2.疾患
3.治療
6 歯科医学的処置
1.補綴,保存,歯科矯正などの処置
B.口腔外科学(松野智宣)
1 構音,摂食,咀嚼の障害と関係のある疾患
1.口唇裂,顎裂,口蓋裂,唇顎口蓋裂および類似疾患
2.舌,口底(口腔底),頬,口唇の異常
3.咬合異常(不正咬合)
4.顎の先天異常,顎変形症
5.顎関節疾患
6.唾液腺疾患
7.末梢神経異常
8.口腔乾燥症
9.口腔内腫瘍
10.口腔粘膜疾患
2 構音,摂食,咀嚼の障害に対する歯科医学的治療法
1.手術的療法
2.補綴的補助装置による機能回復
3.訓練
3 歯,口腔,顎,顔面の炎症,感染症,腫瘍,嚢胞,外傷ならびに治療後の欠損
1.機能障害
2.治療
3.再建と機能回復
4 中枢性疾患による口腔機能障害
1.障害
2.評価
3.治療
5 加齢による口腔機能障害
1.障害(口腔機能低下症)
2.評価
3.治療
II 心の働き
1.認知・学習心理学(板口典弘)
1 感覚と知覚
1.感覚の種類
2.感覚の強度
3.感覚の変容と適応
4.視知覚
5.適応的な知覚処理
6.感覚統合・知覚運動協調
2 学習
1.条件づけのモデル
2.条件づけ以外の学習
3 記憶
1.記憶の処理
2.記憶の分類
4 認知
1.表象,概念
2.スキーマ
3.思考
4.対人認知と態度
5.情動
5 言語
1.象徴と記号
2.コミュニケーション
3.言語と思考
2.臨床心理学(今井正司)
1 パーソナリティ理論
2 異常心理
1.異常心理と臨床症状
2.パーソナリティ障害
3.異常心理の原因
4.防衛機制
5.ストレス対処モデル
3 発達各期における心理臨床的問題
1.緘黙症・不登校・ひきこもり
2.摂食障害
4 臨床心理学的アセスメント
1.精神症状のアセスメント
2.行動のアセスメント
3.知的能力のアセスメント
4.性格のアセスメント
5 心理療法
1.精神分析療法
2.クライエント中心療法
3.家族療法
4.行動療法
5.認知療法
6.認知行動療法
7.新世代認知行動療法
8.遊戯療法
9.集団心理療法
10.心理療法の効果
3.生涯発達心理学(常田秀子)
1 発達の概念
1.発達の規定要因
2.発達研究法
3.発達理論
2 新生児期・乳児期
1.知覚・認知の発達
2.運動の発達
3.愛着(アタッチメント)の発達
3 幼児期・児童期
1.遊びと社会性の発達
2.認知機能の発達
3.自己・他者認知の発達
4.保育・学校教育と発達
4 青年期
1.親子関係・友人関係
2.自我同一性の確立
3.知的機能の発達
5 成人期・老年期
1.職業生活
2.家族生活
3.加齢
4.知的機能
5.死への対応
4.心理測定法(柴田 寛)
1 精神物理学的測定法(心理物理学的測定法)
1.測定対象
2.測定方法
3.測定の誤差
2 尺度水準
1.尺度水準の分類
2.尺度水準ごとの操作
3 尺度構成法
1.尺度構成法とは
2.因子分析
4 テスト理論
1.標準化
2.信頼性
3.妥当性
5 調査法
1.質問紙法
2.サンプリング
6 データ解析法
1.記述統計
2.推測統計
3.統計的検定
III 言語とコミュニケーション
1.言語学(松井理直)
1 言語の基本的性質
1.言語とは何か
2.差異に基づく記号体系としての言語
3.自由度が高く創造性をもつ記号体系としての言語
4.ある社会共同体で共有される表現手段としての言語
5.個人の能力としての言語
6.言語におけるラングとパロール
7.共時態と通時態
8.日本語の語種(語層):和語・漢語・借用語
2 記号体系としての言語
1.言語のシニフィエ:外延と内包
2.言語のシニフィアン:音声と文字
3.シニフィエとシニフィアンの関係:恣意性と有契性
4.記号の範列的関係と統合的関係
5.シンボル化能力としての比喩:メタファーとメトニミー
3 言語の生産性を支える性質
1.二重分節性
2.線条性
3.規則性
4.再帰的階層構造
5.言語生産における無標性と有標性
4 言語記号のシニフィアン:音韻と文字
1.音声と音韻
2.東京方言の音素
3.モーラと音節
4.対立・自然類と弁別素性
5.東京方言のアクセント核
6.東京方言の品詞とアクセント核
7.日本語における文字
5 形態論と語構造の形成
1.形態素:言語記号の最小単位
2.膠着語としての日本語:形態素からみた言語類型論
3.形態素の分類
4.単純語と合成語
5.合成語における形態素の関係性と主辞
6.異形態
7.連濁
8.複合語アクセント規則
9.動詞の形態素:母音語幹動詞と子音語幹動詞
6 統語論・文法
1.日本語の語順:主辞後置型言語
2.品詞と文の種類
3.格助詞
4.n項述語(自動詞・他動詞)と格助詞
5.対格型言語としての日本語
6.内の関係節・外の関係節と格助詞
7 動詞形態素と関わる文法要素
1.時制(テンス)
2.絶対時制と相対時制
3.アスペクト(相)
4.ヴォイス(態)
5.否定(極性・ポラリティの一種)
8 意味論・語用論
1.意味と発話状況
2.語の意味関係:上位語・下位語・同位語
3.類義語と反義語
4.多義語と同音異義語,同訓異字
5.直示表現(ダイクシス)
6.文の論理的な意味:命題
7.話し手の心理的態度:モダリティ
8.話し手と聞き手における情報管理
2.音声学(小松雅彦)
1 音声
1.言語と音声
2.音声と音韻
2 発声発語器官と構音
1.構音器官
2.構音の観察
3 音声記号
1.国際音声記号(IPA)
4 分節音
1.母音
2.子音
3.IPAのその他の記号
4.音声連続
5 音素と異音
6 音節とモーラ
7 超分節的特徴(プロソディ)
1.アクセント(語アクセント)
2.イントネーション
3.リズム
8 日本語音声学
1.日本語の分節音
2.日本語の音節
3.日本語の超分節的特徴
3.音響学(荒井隆行)
1 音とは
1.波の基本
2.疎密波と音圧
3.音波の性質
4.音波の波長・周期・周波数・音速
5.単振動と純音
6.音圧レベルと音の大きさのレベル
2 時間波形と周波数スペクトル
1.純音の場合
2.周期的複合音の場合
3.非周期音の場合
3 音響管の共鳴
1.一様音響管
4 音声生成の音響理論
1.線形時不変システム
2.音源(ソース)フィルタ理論
3.音源の特性
4.声道の伝達特性
5.放射特性
5 音声の信号処理
1.デジタル信号処理
2.AD変換とDA変換
3.標本化定理
4.スペクトル分析
5.サウンドスペクトログラム
6 音声の音響分析
1.母音の音響特性と知覚
2.子音の音響特性と知覚
3.連続音声中の母音と子音
4.超分節的要素の音響特徴と知覚
4.聴覚心理学(世木秀明)
1 音の心理物理学
1.聴覚閾値,痛覚閾値,可聴範囲
2.音の大きさ(ラウドネス)
3.音の高さ(ピッチ)
4.音色
5.弁別閾と比弁別閾
6.持続時間の短い音(短音)の知覚
7.時間的パターンの知覚
2 聴覚の周波数分析とマスキング現象
1.同時マスキングと聴覚フィルタ
2.継時マスキング
3.両耳間マスキングと中枢性マスキング
3 両耳の聞こえ
1.両耳加算効果
2.音源定位
3.カクテルパーティー効果
4 環境と聴覚
5.言語発達学(瀬戸淳子)
1 言語発達を説明する理論
1.生得説
2.学習説
3.認知説
4.社会・相互交渉説
2 前言語期の発達
1.コミュニケーション行動の発達
2.発声行動・言語音知覚の発達
3.認知機能の発達
3 幼児前期の言語発達
1.初語の出現・語彙の増加
2.言語発達を促す大人の関わり
3.構文の発達
4.象徴機能の発達
4 幼児後期の言語発達
1.語彙・構文の発達
2.談話能力の発達
3.音韻意識の発達
5 学童期の言語発達
1.読み書き能力の発達
2.語彙・構文の発達
3.談話能力の発達
IV 社会保障・教育とリハビリテーション
社会保障・教育とリハビリテーション(岡部 卓)
1 社会保障制度
1.社会保障と社会福祉
2.社会保障の体系と範囲
3.社会保障を構成する各制度
4.社会福祉の法律と施策および運用
5.障害者福祉に関する施策の実施
6.介護保険
7.社会福祉援助技術
8.社会保障の実施体制
2 リハビリテーション概論
1.リハビリテーションと障害論
2.リハビリテーションの分野
3 医療福祉教育・関係法規
V 言語聴覚障害学総論
言語聴覚障害学総論(深浦順一)
1 言語聴覚士の歴史と現状
1.歴史
2.現状
2 言語聴覚士の業務と職業倫理
1.業務
2.連携
3.職業倫理
4.障害者の権利
5.リスクマネジメント
3 言語聴覚障害,摂食嚥下障害の特徴と種類
1.特徴
2.種類,原因
3.発生率,有病率
4 言語聴覚療法の実際
1.評価・診断
2.訓練,指導,助言,その他の援助
VI 失語・高次脳機能障害学
1.失語症(中川良尚)
1 失語症の定義
2 失語症の原因疾患と病巣
3 言語症状と失語症候群
1.発話面の障害
2.聴覚的理解面の障害
3.復唱の障害
4.読字の障害
5.書字の障害
6.その他の一般症状
7.古典的失語症候群(失語症タイプ分類)
8.その他の失語症
9.後天性小児失語
10.原発性進行性失語(primary progressive aphasia:PPA)
11.純粋型
4 失語症の評価・診断
1.評価・診断過程
2.評価法
3.評価のまとめ(評価サマリー)
4.診断手続き
5 失語症の訓練・援助
1.リハビリテーション過程
2.言語訓練の理論と技法
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:31.6MB以上(インストール時:84.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:126.6MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:31.6MB以上(インストール時:84.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:126.6MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784263266908
- ページ数:484頁
- 書籍発行日:2025年2月
- 電子版発売日:2025年2月6日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍アプリが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。