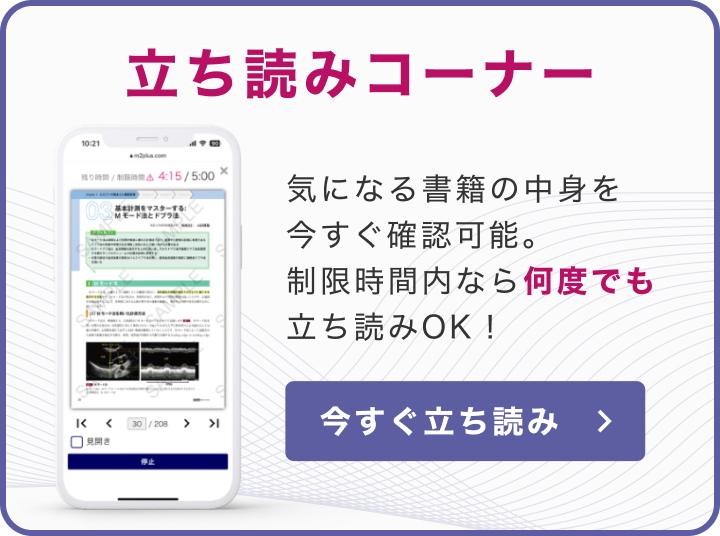- m3.com 電子書籍
- 小説みたいに楽しく読める栄養学講義
商品情報
内容
何をどのくらい食べればいいの?栄養価の高い食物ってなに?栄養素を摂り過ぎたり,足りないと体はどうなる?毎日の食にかかわる知識を基礎からわかりやすく解説します.人の健康を支える栄養学の世界へようこそ
序文
はじめに
■ご飯を食べると馬鹿になる
小学生時、ある日、先生が授業前に、突然、子ども達に質問したことを覚えています。
「皆、目をつぶって。今日、朝、パンを食べた人?」何のことかわからず、私は手を上げました。先生は、上げた者の数を数えて「やっぱしそうか」とつぶやいて、そのまま授業を開始したのです。この質問は、何だったのか、気になっていました。
1960年代、ある本がベストセラーになりました。著者は慶応大学医学部生理学教授の林髞のカッパブックス「頭のよくなる本」です。彼は、大脳生理学の立場から、頭のよさは大脳の活性により決定され、それには、タンパク質、特にアミノ酸の作用が関与していることを説明し、糖質ばかりの米を主食にする日本人の大脳の活性化は低いと主張したのです。
この話は誇張されて、「ご飯を食べると馬鹿になる」といわれるようになり、パン食の優位性が広まり、あの戦争に負けたのも、栄養価の低いご飯を食べていたからだといわれるようになっていたのです。
小学生のときに経験した奇妙な質問は、この説を信じた先生がクラスの子ども達で確かめたかったのでしょう。後に、薄眼で見ていた友達から、約50人のなかで3〜4人が手を上げたと名前を教えてくれました。確かに、私をのぞいては比較的日頃から活発で成績がよかった子ども達だったのです。現在の栄養学でも、栄養不良にある子どもたちは、体格や学習能力が劣るとするデータはありますが、ご飯よりパンの方が大脳の活性を高めるというデータも論拠もありません。我が家の朝食がパン食だったのは、ハワイに移民した親戚のおじさんが戦後で貧しい生活をしていた私たちにコーヒーやグラニュー糖、さらに衣服などを送ってきてくれていたからであり、私の成績も勉強が嫌いだったので優秀ではありませんでした。
■日本人がパン食を導入したきっかけ
脳や神経系の代謝に栄養状態が関与していることは間違いありません。第二次世界大戦中、ミネソタ大学のアンセル・キーズらが行った「ミネソタ飢餓実験」からも明らかです。この実験は、兵役が免除されることを条件に応募した健常人36人が参加し、1944年から実施されました。通常の半分の食事(約1570㎉)で6カ月間実験が行われた結果、すべての対象者の体重は25%以上減少しました。さらに、貧血、疲労、無気力、極度の脱力感が起こると同時に、過敏性、イライラ感、うつ症状、集中力の低下などの神経学的欠損が出現したのです。しかし、このことをパン食とご飯食の違いにすることには問題があります。主食をパンにする欧米人にも、ご飯を主食にする日本人にも、低栄養と過栄養は存在し、全体的な栄養状態を限られた食品どうしで比較することはできません。
そもそも、日本人がパンを日常的に食べるようになったのは、戦後の米不足のなかで輸入の小麦粉を主食にせざるを得ない理由があったからです。当時、B-29の爆撃により国土は焼土化し、農業は壊滅して食べものが完全に不足していたのです。
1954年、「米国余剰農産物受け入れに伴う、市場開拓費の使途」の調査団が来日しました。米国は、農業技術の改革で食料増産が起こり、輸出先を探していた矢先でした。当初、日本側は、伝統的な食習慣であるご飯食からパン食への切り替えは困難だと主張しました。
何度もの交渉の末、輸入食料の代金の一部に宣伝普及費を入れる条件で妥結したのです。じつは、日本はこのお金で、講習会やキッチンカー(調理デモができる栄養教育車)を購入して食生活の改善運動を全国的に展開したのです。
■栄養学を正しく学ぶ必要性
栄養士と食生活改善普及員(現:ヘルスメイト)などを中心に、輸入食料の活用を織り混ぜた栄養教育がはじまり、一方では、学校給食や病院給食の献立にパン食が導入され、この事が欧米食が日本に普及するトリガーになっていったのです。
パン食は、日本人を米国の食料政策の枠組みに組み込む長期戦略だったという意見があります。しかし、当時の日本には、食料が絶対的に不足し、1942年(昭和17年)に制定された「食糧管理法」がすでに機能しなくなっていました。例えば、1947年(昭和22年)には、衝撃的事件が起こります。東京地方裁判所の山口良忠判事が、法律を守る立場にある正義感から、違法になる闇米を拒否して栄養欠乏症により餓死したのです。当時、大きなニュースになりました。
米国の「食料政策」を、日本は、食料の安定供給に留まらず、日本人に不足していたエネルギー、タンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラルなどの供給策として活用して、栄養バランスの優れた食事につくりあげていったのです。いわば、「栄養政策」に変換したといえます。
このことは、日本人の体格や体力を増強するとともに、その後、高度経済発展によって起こった過栄養や肥満、さらに非感染性疾患の増加にブレーキをかけて、世界一の長寿国家を建設する一助になったのです。このような事例は、国際的に珍しく、私はこのことを「ジャパン・ニュートリション」と総称し、多くの人々に栄養の重要性と栄養学を正しく学ぶことの必要性を世界に発信しています。
目次
はじめに
第1章 栄養学とは
栄養・栄養学とはなにか
栄養学の歴史
人体の構成と栄養
細胞・遺伝子と栄養
食物の成分と栄養
保健と栄養
医療・福祉と栄養
第2章 栄養素の種類と働き
タンパク質―人体を構成する主成分
脂質―多種多様な種類がある
炭水化物―最大のエネルギー源
ビタミン―体にとっての潤滑油
ミネラル―体を調整し、材料にもなる
タンパク質の働きと欠乏症・過剰症
脂質の働きと欠乏症・過剰症
糖質の働きと欠乏症・過剰症
食物繊維の働きと欠乏症・過剰症
ビタミンの働きと欠乏症・過剰症
ミネラルの働きと欠乏症・過剰症
水の働きと摂取量
第3章 栄養素の生理
食物の摂取
食欲中枢とその調整機能
空腹感とはなにか
食欲と空腹感は別物
味覚
栄養感覚による摂取量の調整
消化
消化器官
吸収
吸収の機構
吸収の経路
排泄
栄養素の消化・吸収
タンパク質の代謝
脂質の代謝
炭水化物の代謝
ビタミンの代謝
ミネラルの代謝
第4章 エネルギー代謝
生命のエネルギーと食物のエネルギー
人体のエネルギー代謝
推定エネルギー必要量の算定
第5章 ライフステージと栄養
妊娠期・授乳期の体の変化
妊娠と栄養
妊娠中に起こりやすい疾患
授乳と栄養
発育期の生理
新生児・乳児の栄養
新生児・乳児の栄養障害
幼児の栄養
幼児の栄養障害
学童期の栄養
思春期・青年期の生理
思春期・青年期の栄養
学童期・思春期・青年期の栄養における問題
成人期の生理
成人期の栄養と生活習慣病
高齢期の生理
高齢者の栄養
高齢者の栄養不良
第6章 傷病者の栄養ケア・特別用途食品と保健機能食品
食事療法
肥満
痩せ
タンパク質欠乏症
ビタミン・ミネラル欠乏症
糖尿病
脂質異常症
高尿酸血症・痛風
高血圧症
貧血
食物アレルギー
がん
外科手術
栄養補給
特別用途食品
保健機能食品
第7章 健康づくりのこれまでとこれから
栄養改善から健康増進へ
健康日本21
食事摂取基準
食生活指針
栄養不良の二重負荷
快適で持続可能な社会の建設と栄養
おわりに:超高齢社会と環境問題、カギは栄養
参考文献
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:6.7MB以上(インストール時:16.3MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:26.8MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:6.7MB以上(インストール時:16.3MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:26.8MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784758121330
- ページ数:208頁
- 書籍発行日:2025年1月
- 電子版発売日:2025年2月18日
- 判:四六判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍アプリが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。