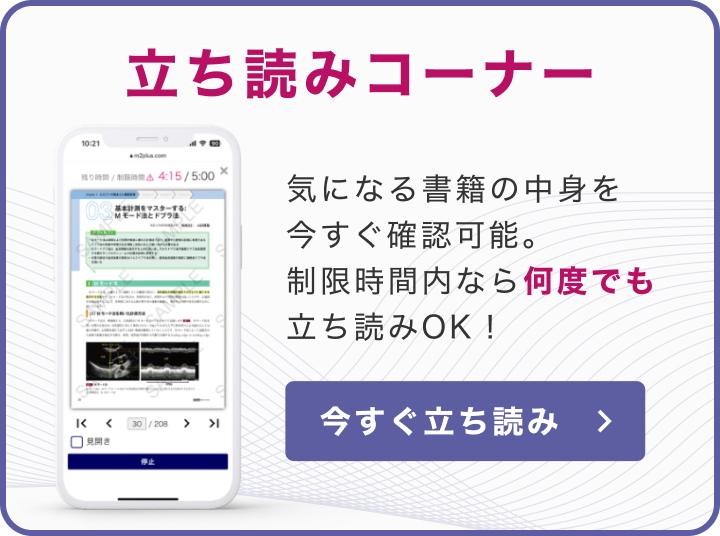- m3.com 電子書籍
- 切断と義肢 第3版
商品情報
内容
●学生から専門家まで,切断・義手・義足に関わる医療従事者に幅広く役立つ,必読・必携の書.
●学ぶべき古典的内容は残しつつ,統計情報,義肢のパーツ,などの記載を更新.
●義手/義足それぞれのリハビリテーションの内容を学びやすいように章を再構成.
●日本義肢装具学会が作成した,新しい「日本版能動義手適合検査表」に対応.
序文
第3版の序
筆者は米国カリフォルニア大学で義肢製作技術を学び,1960年に帰国した.神戸医科大学に復帰後,兵庫県立身体障害者更生相談所の年30回にわたる巡回相談に参加して,県下5,000人の切断者の義肢の処方判定業務に就き,多くの切断者の自宅・職場を訪ねた.切断者の日常生活から多くを学び,それ以後「切断者こそわが師,地域が教科書」を座右の銘としている.
この経験を基に,『切断と義肢』は1973年に,リハビリテーション医学全書(医歯薬出版)の第18巻として出版された.その後,切断術・義肢装着訓練・義肢のめざましい進歩に応じて3回の改訂を行った.しかし,本書の第1版の序に述べているように,この間の切断と義肢に関わる技術の進歩が著しく,そのうえわが国の独特の日常生活動作,とくに正座,あぐら,玄関での靴の脱履動作に適応する義足の研究開発に従事した結果を紹介したく,内容が増えたために,2007年に医歯薬出版と相談して,リハビリテーション医学全書のシリーズを離れて,単行本とする形で本書の第1版を発行することとなった.
その後,切断と義肢をめぐる日進月歩の情報を読者の皆さまにお届けするために頻繁に小規模な内容更新を重ねてきたが,2016年に兵庫県立総合リハビリテーションセンター,神戸医療福祉専門学校三田校(ISPO日本支部)などの協力を得て,第2版の改訂を行った.
近年は,シリコーンをはじめ新たな材質や各種継手の開発など,まさに日進月歩の著しい発展が続いている.そのような情報については,オットーボック・ジャパン株式会社の深谷香奈氏,八幡済彦氏,オズールジャパン合同会社の楡木祥子氏,金子正一氏,株式会社佐藤技研の佐藤拓郎氏をはじめとするメーカー各社にご協力をいただき,新製品のご紹介をいただいたことを深謝したい.また,野坂利也氏(北海道科学大学)には国内で入手可能な足部・継手をご紹介いただき,重ねて御礼を申し上げたい.申すまでもなく,筆者が所属している兵庫県立総合リハビリテーションセンターにおいては,陳 隆明氏,戸田光紀氏をはじめとする義肢装具研究班(理学療法士・作業療法士)の方々,義手の情報・写真を提供いただいた浜本雄司氏(株式会社近畿義肢製作所),増田章人氏(株式会社近畿義肢製作所),高橋功次氏(有限会社タカハシ補装具サービス),小林伸江氏(専門学校川崎リハビリテーション学院),義足の情報・写真を提供いただいた佐野太一氏(株式会社澤村義肢製作所)に心から感謝を申し上げる.
義肢の適合技術が進歩してきた一方では,義手の適合判定基準は長年の経緯のなかで不統一となっている点が散見され,とくに,完成した義手が果たして処方通りに製作されているか,また,能動義手が切断者により十分な機能を発揮できているかが問題視された.その結果,能動義手の適合検査の統一化が重要な研究課題となった.そこで,日本義肢装具学会は特設委員会「義手適合判定検討委員会」を設置し,現状で使用されている義手の適合判定を再検討し,新しい日本版の適合判定(チェックアウト)検査表と手順書・解説動画を作成することとなった.
そこで,本書『切断と義肢』においては,すでに第3版改訂に取り組んでいたのだが,できれば日本義肢装具学会での最終報告を待って新しい能動義手の適合判定を掲載し読者に正確な情報を伝えたいと考え,第3版改訂を遅らせることとした.それと同時に,従来の第2版までは上肢切断・義手と下肢切断・義足が整理不十分のままに掲載されており,とりわけ上肢切断・義手の抜本的な見直しが必要となった.幸い,上肢切断のリハビリテーションをライフワークとして,過去30年以上にわたって著者の盟友として兵庫県立総合リハビリテーションセンターで約100名の筋電義手装着訓練を担当してきた,リハビリテーション療法部次長兼主任作業療法士の柴田八衣子氏から貴重な協力をいただき,以下の通り第3版改訂の骨子とした.
本書の構成は,第1章ではわが国における切断者のプロフィールや切断の原因となる疾病や障害,切断手技や切断高位の選択,先天性奇形など,「切断」を学習するための基本を示した.第2章では,多職種協働で行う切断者のリハビリテーションの過程や断端ケア,義肢装着の開始時期など,「切断者のリハビリテーション」に関わるすべての医療従事者に対しての心得を示した.第3章では,義肢の分類や装着・適合・アライメントなど「義肢に関する基本的な事項」として必要な知識を示した.第4章「義手」では義手と上肢切断者へのリハビリテーション,第5章「義足」では義足と下肢切断者へのリハビリテーションの実践について具体的に解説した.第6章「わが国内外における義肢装具発展のあゆみ」では,国内における義肢装具発展のあゆみとして筆者が携わった歴史,および海外との関わりについて紹介した.
これらが,切断と義肢を学ぶ初学者から,長年にわたって切断・義手・義足に携わっておられる臨床・教育・研究現場などの関係者に至るまで,すべての方に役立てば幸いである.
今回の第3版改訂は,読者目線に立った各章間の内容調整,義手の適合判定などにおいて数多くのアドバイスをいただき実行された柴田八衣子氏のご尽力無しではなし得なかった.感謝申し上げたい.
最後に,長きにわたって終始細心のご尽力をいただいた医歯薬出版編集部および関係者の皆さまに深謝申し上げる.
2025年1月
澤村誠志
兵庫県立総合リハビリテーションセンター名誉院長
神戸医療福祉専門学校三田校校長
元ISPO(国際義肢装具協会)会長
目次
第1章 切断
1 わが国における切断者のプロフィール
1 わが国における切断者の発生率
2 兵庫県における切断者の疫学調査
3 海外における切断者の疫学調査
2 切断の原因となる疾患・障害
1 末梢動脈疾患
1 末梢動脈疾患とは
2 末梢動脈疾患の臨床症状
3 末梢動脈疾患における末梢血行の測定方法
4 末梢動脈疾患の治療
5 切断高位の決定
6 末梢動脈疾患による切断後の予後
2 重度の外傷:患肢温存か切断か
3 悪性骨腫瘍:切断から患肢温存へ
3 切断高位の選択
1 上肢切断高位の選択
1 肩部の切断
2 上腕部の切断
3 肘部の切断
4 前腕部の切断
5 手部の切断
6 指の切断
2 下肢切断高位の選択
1 仙腸関節離断,解剖学的股離断の選択(義足装着による能力差)
2 機能的・義肢学的股離断(大腿骨頸部,転子下切断)の選択
3 大腿短断端の選択
4 大腿長断端の選択
5 膝離断の選択
6 下腿短断端の選択
7 下腿長断端の選択
8 サイム切断の選択
9 足部切断の選択
4 切断手技の最近の傾向
1 皮膚の処理
2 血管の処理
3 神経の処理
4 骨の処理
5 筋肉の処理
6 切断術実施前に,将来装着する義肢の処方を明確に指示
5 各切断部位の切断手技
1 上肢
1 肩甲胸郭間切断
2 肩離断
3 上腕切断
4 肘離断
5 前腕切断
6 手部および指での切断
7 特殊な切断
2 下肢
1 骨盤部での切断
2 股離断
3 大腿切断
4 膝離断
5 下腿切断
6 足関節離断─サイム切断
7 ボイド切断,ピロゴフ切断
8 足部切断─ショパール関節離断
9 足指切断
6 先天性奇形・切断
1 分類
1 O'Rahilly,Frantz,Aitkenによる分類
2 ISO/ISPOの分類
2 症例
3 先天性の欠損に対する基本的な考え方
第2章 切断者のリハビリテーション
1 リハビリテーションとは
2 切断者のリハビリテーションの過程
1 医学的リハビリテーション
2 心理的リハビリテーション
3 社会的リハビリテーション
4 職業的リハビリテーション
3 多職種協働による切断義肢クリニック
1 切断義肢クリニックの機能
2 クリニックチームメンバーの役割
4 切断直後の断端のケア
1 切断術直後の断端創の処置
1 ソフトドレッシング(soft dressing,弾性包帯)
2 リジッドドレッシング(rigid dressing,ギプスソケット)
3 リムーバブルリジッドドレッシング(removable rigid dressing:RRD)
4 リジッドドレッシングを利用した後にシリコーンライナーを用いる方法
5 創治癒後にシリコーンライナーを用いた早期義肢装着法
2 切断術直後の断端ケアの方針
5 義肢装着開始の時期
1 在来式義肢装着法(delayed prosthetic fitting)
2 術直後義肢装着法(immediate postoperative prosthetic fitting)
3 早期義肢装着法(early prosthetic fitting)
6 義肢の処方
7 断端の異常と合併症
1 断端痛
2 幻肢および幻肢痛
3 断端における皮膚疾患
4 断端の拘縮と発生の予防
5 断端の浮腫と予防
8 断端の衛生保持
第3章 義肢に関する基本的な事項
1 義肢とは
2 義肢の分類
1 義肢の構造による分類
2 義肢の機能面からみた分類
3 切断術後の装着する時期による義肢の分類
3 義肢の装着・適合・アライメントなど基本的な事項
1 ソケットの適合
2 義肢のアライメント(alignment)
4 義肢素材,特に合成樹脂材料について
第4章 義手
1 義手に関する基本的な事項
1 上肢切断の部位・測定方法と義手の名称
1 切断の部位と断端長(stump length)
2 関節可動域の測定
3 義手の長さの決定
2 義手の機能
3 機能面からみた義手の分類
1 装飾用義手(cosmetic upper-limb prosthesis)
2 作業用義手(work arm,Arbeitsarm)
3 能動義手(functional upper-limb prosthesis)
2 義手の構成と部品
1 ソケット
2 支持部
1 殻構造,骨格構造
2 上腕支持部,前腕支持部
3 ハーネス
4 コントロールケーブルシステム(control cable system,Kraftzugsystem)
5 継手(joint)
1 肩継手
2 肘継手
3 手継手
6 手先具(terminal device)
1 装飾用手先具
2 作業用手先具
3 能動フック(utility hook,Greiger-hook)
4 市販されている能動フックの種類
5 能動ハンド(utility hand,Kraftzug-Hand)
6 電動ハンド
3 肩離断と義手
1 切断部位と機能的特徴
2 肩義手ソケットの適合
1 ソケットの種類
2 ソケットの採型と適合
3 肩義手のアライメント
4 ハーネスとコントロールケーブルシステム
5 操作性向上のための工夫
6 肩継手に能動単軸肘ブロック継手を用いた肩義手
4 上腕切断と義手
1 切断部位と機能的特徴
2 上腕義手ソケットの適合
1 ソケットの種類
2 ソケットの採型と適合
3 上腕義手のアライメント
4 ハーネスとコントロールケーブルシステム
1 上腕義手における基本的なハーネスとコントロールケーブルシステム
2 その他の上腕義手のハーネスとコントロールケーブルシステム
5 前腕切断と義手
1 切断部位と機能的特徴
2 前腕義手ソケットの適合
1 ソケットの種類
2 ソケットの採型と適合
3 前腕義手のアライメント
4 ハーネスとコントロールケーブルシステム
1 前腕義手における基本的なハーネスとコントロールケーブルシステム
2 両前腕義手のハーネスとコントロールケーブルシステム
6 手部切断(手根骨離断・中手骨切断・手指切断)と義手
1 切断部位と機能的特徴
2 手部切断(手根骨離断・中手骨切断・手指切断)の義手
1 手根中手骨切断の場合
2 全指切断の場合
3 母指切断の場合
4 母指以外の手指切断の場合
3 手指切断におけるリハビリテーション
7 能動義手の適合検査
1 身体機能検査
2 義手検査
3 義手装着検査
4 義手操作適合検査
8 義手装着訓練
1 装着前訓練
1 創の良好な治癒と成熟断端の早期獲得
2 関節可動域の確保
3 良好な姿勢の確保
4 筋力増強訓練
5 断端訓練
2 義手コントロール訓練
1 前腕義手
2 上腕義手
3 肩義手
3 義手使用訓練─基本訓練
1 義手手先の位置の設定(prepositioning of terminal device)
2 “どちら側が利き手か”の決定
3 訓練は,単純なものから複雑なものに
4 義手使用訓練─日常生活動作
1 衣服着脱動作
2 食事動作
3 事務動作
4 整容動作
5 家事動作
6 自動車運転
9 筋電電動義手
1 筋電電動義手の特徴と背景
2 筋電電動義手の構成と部品
1 筋電電動義手の基本的構造
2 制御用信号源
3 システムコントロール
4 制御方法
5 バッテリー
6 手先具
3 日本で取り扱われている筋電義手
1 MYOBOCK(R) ハンド成人用と小児用
2 bebionic Hand
3 Michelangelo hand(R) ミケランジェロハンド
4 i-Limb(R) hand
5 i-Digits Quantum
4 わが国における前腕切断に対する筋電電動義手
5 筋電電動義手の公的交付の変化
6 上腕電動義手
10 筋電電動義手の装着訓練とメインテナンスの実際
1 義手装着前訓練の評価と訓練について
2 訓練用筋電電動義手(仮義手)の製作
3 仮義手訓練
4 メインテナンス
5 筋電電動義手利用者の立場に立って─筋電電動義手装着を成功に導くためには─
6 筋電電動義手を装着利用されている具体的事例
第5章 義足
1 義足に関する基本的な事項
1 下肢切断の部位・測定の方法と義足の名称
2 義足継手と足部
1 股継手
2 膝継手
1 膝継手軸の形状による分類
2 立脚相の制御(stance phase control)
3 遊脚相制御(swing phase control)
4 インテリジェント義足
5 最近におけるハイブリッド型膝継手の開発実用化
6 膝継手の機能区分整備(厚生労働省障害者対策総合研究事業;平成27年)
7 膝継手の処方(選択)
3 足継手と足部
1 中足指節関節の底背屈運動
2 距腿関節の底背屈運動
3 足根間および足根中足関節の回内外運動
4 エネルギー蓄積型足部(energy storing foot)
5 義足足部の臨床比較
6 スポーツ用義足足部
7 トルクアブソーバー
8 国内で入手可能な義足足部
3 義足の理解に必要な正常歩行について
1 歩行周期
1 立脚相
2 遊脚相
3 両脚支持期
2 歩行の基本的要因
3 歩行における下肢の回旋
4 歩行における筋肉の働き
5 歩行における床反力
6 義足歩行におけるエネルギー消費
7 義足歩行に必要な4つの条件
4 股義足
1 受皿式およびティルティングテーブル式の股義足
2 カナダ式股離断用股義足
1 特徴
2 歩行の特徴
3 製作方法
4 歩行能力と実用性
5 殻構造義足から骨格構造義足への移行
6 継手の処方
5 片側骨盤切断(仙腸関節切断)用義足
1 特徴
2 製作過程
3 歩行能力
4 膝継手および足部の処方
6 大腿義足
1 大腿義足の種類と変遷
2 吸着式ソケット
1 吸着義足の利点
2 初期の吸着式ソケット
3 open end socketから全面接触ソケットへ
4 全面接触ソケットの利点
3 四辺形吸着式ソケット
1 円形から四辺形ソケットへ
2 断端に対する四辺形吸着式ソケットの機能的役割
3 木製ソケットから合成樹脂ソケットへ移行
4 合成樹脂製ソケットの処方および製作上必要な断端の諸検査
5 坐骨結節支持レベルでのソケットパターンの概略の決定
6 大腿ソケット適合上の愁訴と原因
4 坐骨収納型ソケット(IRCソケット)
1 四辺形ソケットから坐骨収納型ソケットへ
2 Normal Shape-Normal Alignment(N.S.N.A.:Ivan Long)
3 CAT-CAM
4 Ishial-Ramal-Containment Socket(IRCソケット:坐骨収納型ソケット)を統一名称に決定
5 坐骨収納型ソケットの機能と形状
6 坐骨収納型ソケットの利点と欠点(四辺形ソケットと比較して)
7 坐骨収納型ソケットの製作
8 M.A.S.(R)(Marlo Anatomical Socket)
5 Flexible Sub-Ischial Vacuum Socket
1 NU-FlexSIVソケットデザインの特徴
2 NU-FlexSIVソケットの製作
3 NU-FlexSIVソケットの不適応例
6 大腿義足のアライメント
1 アライメントの決定方法
2 膝の安定性
3 大腿義足の側方安定性(mediolateral stability)
7 大腿義足における義足歩行異常とその原因
8 大腿義足の懸垂方法
1 シレジアバンド
2 股ヒンジ継手と骨盤帯
3 シリコーンライナーによる懸垂
9 大腿吸着義足の適応例
10 わが国の大腿切断者の悩みとその解決方法
1 日本の日常生活動作への適応
2 高齢大腿切断者に対する軽量化,適合調節に関する問題
3 水泳・入浴用大腿義足
4 農耕用大腿義足
7 膝義足
1 膝離断用ソケットの適合
1 在来式ソケット
2 軟ソケット付き全面接触ソケット
2 膝義足の遊脚相制御
8 下腿義足
1 機能的特徴とその機能を生かすための条件
1 下腿切断の機能的特徴
2 下腿切断後の残余機能を最大限に生かす下腿義足の条件
2 下腿義足の進歩の歴史
3 PTB下腿義足
1 PTB下腿義足の構成
2 PTB下腿義足の特徴
3 PTB下腿義足の採型とソケットの製作
4 PTB下腿義足のアライメント
5 PTB下腿義足の特性(利点・欠点)と処方方針
6 エアクッションソケット付きPTB下腿義足
4 PTS下腿義足
5 KBM下腿義足
6 TSB吸着下腿義足
1 TSB吸着下腿義足の特徴
2 TSB吸着ソケットの適合理念
3 TSB吸着ソケットのギプス採型手技の基本
4 インターライナーの開発・進歩
5 代表的なシリコーンライナー
6 TSBソケットの適合上によく起こる問題点と対策
7 シリコーンライナー適用への円滑な移行
9 サイム義足
1 サイム切断のもつ機能的特徴
2 サイム義足の種類
1 在来式サイム義足
2 カナダ式合成樹脂製サイム義足
3 VAPC内側開き式サイム義足
4 軟ソケット付き全面接触式サイム義足
3 サイム義足用足部
10 足部切断と義足
1 足部切断のもつ問題点
1 わが国において足部切断が多い理由
2 ショパール・リスフラン関節離断部位に対する評価
2 足部切断用義足
11 3D-CAD/CAMによる義足ソケットの製作
12 義足装着訓練
1 義足装着前訓練
1 断端訓練
2 健常な姿勢の保持
3 体幹筋訓練
4 下肢切断者の健脚訓練
5 水治療法およびマッサージからシリコンライナー装着へ
2 義足装着前後の断端の評価
3 義足の適合検査
4 義足装着訓練
1 義足の装着
2 立位での平衡訓練
3 平行棒内での平衡訓練
4 歩行訓練
5 日常生活動作訓練
6 応用・習熟訓練
7 両下肢切断者の歩行訓練の特殊性
8 下肢切断者の歩行能力
9 義足装着訓練ステップアッププログラムについて
第6章 わが国内外における義肢装具発展のあゆみ
1 障害者福祉施策の動向
1 わが国の障害者数
2 わが国の障害保健福祉施策の歴史
3 国連障害者権利条約批准へ
2 わが国における義肢装具発展のあゆみ
1 日本義肢装具研究同好会から「日本義肢装具学会」発足へ
2 日本リハビリテーション医学会および日本整形外科学会に設置された義肢装具委員会の協働による行政への提言と,これにより実施された義肢装具サービスの改革
3 義肢装具の価格体系の変遷と今後の改革について
4 福祉用具法
5 義肢装具研究開発と地域リハビリテーションサービスの向上にむかって
3 義肢装具における国際協力のあゆみ
1 ISPO(国際義肢装具協会)の目的と組織
2 わが国の義肢装具における今後の国際協力のあり方
文献
和文索引
欧文索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:661.8MB以上(インストール時:1.3GB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:2.6GB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:661.8MB以上(インストール時:1.3GB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:2.6GB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784263266915
- ページ数:584頁
- 書籍発行日:2025年2月
- 電子版発売日:2025年4月29日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍アプリが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。