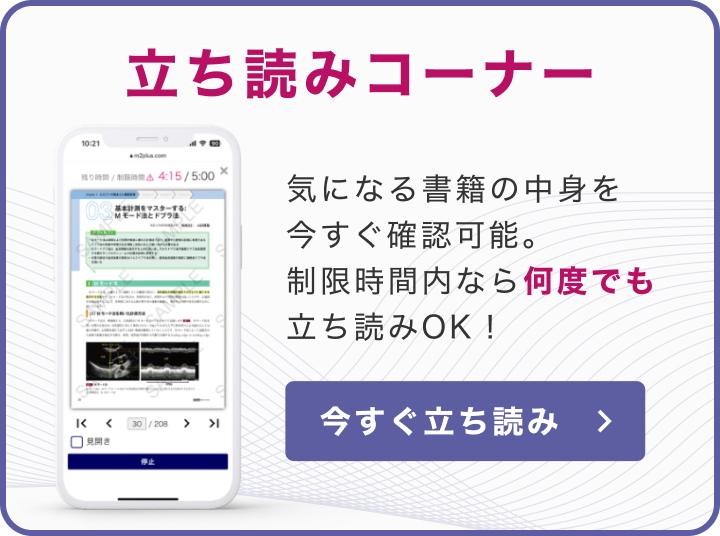- m3.com 電子書籍
- 運動学習の知識を活かす神経リハビリテーション実践 -回復への最適解を探る-
商品情報
内容
「人が運動を学ぶことは、自己に可能性を与えること」である。
これは、運動学習について日々学び、研究や臨床を通して思考を深めている本書の著者たちの考えです。このような観点をもって、リハビリテーションにおける運動学習についての知識を基礎から体系的にまとめ、臨床での活かし方を提示しています。
理学療法士や作業療法士にとって「運動学習」はなじみのある言葉ですが、養成教育のなかで体系的に学ぶ機会はほとんどありません。本書は、リハビリテーションの観点から運動学習について網羅的・体系的にまとめ、臨床での課題設定や介入方法を提示し、具体的な症例を通して実際の運用でのポイントを示しています。
効果的なリハビリテーションは、その人にとって最適な学習課題と学習環境をいかに整えられるかにかかっています。そのためには身体面だけでなく精神・心理的な側面など多岐にわたる要因を考慮する必要があります。それらを「運動学習」という視点で貫くことで、これまで個別に学んできたさまざまな知識がつながり整理されてきます。そこから、日々の臨床において、多要因を考慮したうえで新たな神経回路をリハビリテーションによっていかに効果的に再構築し、最終的な運動(パフォーマンス)の質を上げるかという探求へつなげていきます。
運動学習の知識を学び、リハビリテーションの実践に活かすことを第一としてまとめられた本書は、「運動学習」についてきちんと学びたい理学療法士・作業療法士にとって最適なテキストです。
序文
はじめに
運動学習(motor learning)は古くて新しいテーマである。人がどのように運動を学習するかについての科学的な探究は、1890年代から行われており、これまで社会的情勢の影響を受けつつ発展してきた。古くは、電信作業(モールス信号の送受信)(Bryan & Harter, 1897, 1899)や航空機の操縦技術(Ammons et al., 1958) がどのように上達するかについて検証されてきた背景がある。その後、本書でも扱う複数の運動学習理論の提唱やその理論に基づいたスポーツ心理学分野での検証が盛んとなった。現代においては、運動学習はスポーツ心理学分野の他、身体教育学、神経科学、そしてリハビリテーション科学で扱う学際的科学となっている。
この広がりを背景に、運動学習理論や運動学習に関する多くの知見が蓄積されている。しかしながら、リハビリテーションにおいて眼前の対象者の運動学習についてどのように分析して臨床推論するのか、また、運動学習に関する知識をどのように効果的に利用するのかといった一連の思考過程の共通認識は得られていない。これは、多くのリハビリテーション専門職にとっての課題であると考えられる。実際に、海外の複数の論文において、運動学習の理論を実践に活かすための方法論の不足や教育資源の不足に関する指摘がある(Levac et al., 2016;Zwicker & Harris, 2009)。つまり、国内外において、その解決への取り組みが必要であると考えられる。以上を勘案すると、リハビリテーション分野における運動学習に関する取り組むべき課題は次にまとめられる。
課題1.運動学習に関する教育資源の提供
課題2.運動学習に関する知識(理論)を実践に活かすための系統的な方法の提案
我々は、これら2つの課題の解決に寄与すべく本書を構成した。つまり、運動学習に関連する多彩かつ詳細な知識を網羅的に扱い、知識や理論をリハビリテーションの実践に活かすことができるような系統的な手法の提案を試みた。
具体的な構成は次の通りである。本書は全11章であり、大きく第1~5章、第6~9章、第10~11章と3つのパートに分かれる。第1~5章は運動学習に関連する基礎的な知識の総まとめである。運動学習に関する定義や諸理論など最も基本的な知識に関しては冒頭の内容とした(第1、2章)。その他の基礎的な知識として、運動学習に関わる感覚運動的側面(第3章)、運動学習に関わる精神・心理的側面(第4章)、運動学習に関する神経科学的な知見(第5章)を扱うこととした。このように前半の第1~5章においては、運動学習に関する基礎的な知識について網羅し、読者の方々の知識のベースアップ、ブラッシュアップを図る内容とした。
続く第6~9章は、リハビリテーション対象者が効率的な運動学習が行えるような関わり方や介入の方法について紹介している。運動学習効率を最大限に高めるために不可欠な課題の設定方法の記述を厚くした(第6、7章)。その後は、運動学習を促進すると考えられるエビデンスが認められた介入方法のパートを設けた(第8章)。さらには、現状エビデンスの確立はされていないが、運動学習に寄与しうる介入方法に関するパートも設けた(第9章)。このように第6~9章は、対象者の運動学習を促すための課題設定や介入方法に特化しており、第11章で提示する症例に対する治療戦略を理解するための布石となる重要なパートとなっている。最後の第10、11章では、運動学習に関する知識の臨床リハビリテーションでの活かし方について、体系的にまとめている。これまで体系立っていなかった、リハビリテーションプロセスにおける運動学習に関する知識の利用の仕方を本書で提案した(第10章)。そして、その内容に基づき、具体的な症例の分析と解釈を行い、どのような運用が可能であるかについて、ポイントが明確になるように記述した(第11章)。
このように全容を概観すると、上記の課題1の「運動学習に関する教育資源の提供」には第1~5章と第6~9章が対応し、課題2「運動学習に関する知識(理論)を実践に活かすための系統的な方法の提案」には第10、11章が対応しているということがおわかりいただけるかと思う。
その他、本書の特徴を3点挙げる。1つ目は、本書の著者は2021年7月から毎月1回行っている運動学習の勉強会に参加するメンバーで構成しているということである。この意図は、書籍を書き進める上で、深いディスカッションを繰り返すことで、内容の充実化と偏向(思考のバイアス)の回避を図ることにあった。実際に月2 回はオンラインミーティングにてディスカッションを行い、常にメッセージツールを使用しながら書き進めることを継続し、入稿に至った。つまり、本書の内容は、勉強会メンバーのコンセンサスが得られた、一貫性のある充実した内容であるということをお伝えしておきたい。
2つ目は、運動学習に関する知識を提供する第1~9章では、各章の末尾にまとめと今後解決すべき課題や、取り組むべき方向性を明示したことである。運動学習に関する研究は古くから行われているが、多くは健常者を対象とした研究である。そのため、それらの知識がそのまま臨床リハビリテーションに応用できるかは未だ不明な点が多いのは事実である。第1~9章では、運動学習に関する知識を網羅的に扱うため、一見あらゆることが明らかになっているという錯覚に陥るかもしれない。しかしながら実際には、特に臨床リハビリテーションを考慮すると、明らかになっていることは非常に限定的であり、今後検証すべきことが山積しているということを認識しておく必要があるだろう。したがって、各章のまとめと課題と方向性を示し、運動学習研究や運動学習に関する知識を活かした臨床リハビリテーションの発展に貢献したいと考えている。
3つ目は、各章の間には、「サプリメント」として運動学習に関する予備的な知識の紹介をしていることである。これは、書籍の構成上、本文に組み込むことはできなかったが、是非読者の方々に知っていただきたい運動学習に関する新しい知識や重要な知識である。本文のみならず、このサプリメントの情報も臨床リハビリテーション遂行上、非常に参考になる内容を集めているため、是非一読してほしい。
本書の企画当初、ターゲットとする読者は、リハビリテーションに関して一通りの経験を積み、後輩の手本となる立場になりつつある年次の療法士であった。こういった療法士が、本書を通じて新たな知識を吸収し、さらに一歩踏み出すきっかけとなるような書籍にしたいと考えていた。しかしながら、我々が本書の執筆を通じて改めて理解したことは、運動学習に関する知識は、臨床リハビリテーションにおける基礎的知識であるとともに、極めて応用的知識であるということである。療法士は、対象者の動作獲得の程度を経時的に判断することが求められるため、運動学習の知識が基礎になる。その一方で、運動学習自体が多要因で構成され、多次元的に絡み合う時間的(経時的)な概念であるため、対象者の運動学習を適切に図るためには卓越した熟練スキルを要する。運動学習の周辺知識について網羅的に扱い、その活用方法を具体的に示している本書は、日頃から注意深く臨床を行い、運動学習に関する熟練スキルの習得を目指す中堅やそれ以上の療法士にも大いに役立つはずである。すなわち、運動学習について学ぼうとする多くの療法士にとって、有意味な書籍に仕上がったと自負している。本書が、少しでも多くの療法士の手に届き、深く読み進めてもらえることを強く願っている。
著者を代表して 川崎翼
Ammons, R. B., Farr, R. G., Bloch, E., et al. (1958). Long-term retention of perceptual-motor skills. Journal of Experimental Psychology, 55(4), 318–328. https://doi.org/10.1037/h0041893
Bryan, W. L., & Harter, N. (1897). Studies in the physiology and psychology of the telegraphic language. Psychological Review, 4(1), 27–53. https://doi.org/10.1037/h0073806
Bryan, W. L., & Harter, N. (1899). Studies on the telegraphic language: The acquisition of a hierarchy of habits. Psychological Review, 6(4), 345–375. https://doi.org/10.1037/h0073117
Levac, D. E., Glegg, S. M. N., Sveistrup, H., et al. (2016). Promoting therapists’ use of motor learning strategies within virtual reality-based stroke rehabilitation. PloS One, 11(12), e0168311. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168311
Zwicker, J. G., & Harris, S. R. (2009). A reflection on motor learning theory in pediatric occupational therapy practice.Canadian Journal of Occupational Therapy, 76(1), 29–37. https://doi.org/10.1177/000841740907600108
目次
【第1部】運動学習を理解するための「基盤的知識」
第1章 運動学習に関する基礎知識(川崎 翼)
1.1 「人が動きを学ぶこと」の本質について
1.2 まずは運動学習の定義から
1.3 運動制御と運動学習の関係を整理する
1.4 運動パフォーマンスの分類を知る
1.5 運動学習の種類を知る
1.6 運動学習過程を知る
1.7 運動学習段階を把握する
1.8 リハビリテーション対象者と健常人の運動学習の違いが重要
1.9 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント1 リハビリテーション科学とスポーツ心理学における運動学習の捉え方〜類似点と相違点(鈴木博人)
第2章 運動学習に関する諸理論(秋月千典)
2.1 コンパレータモデル〜運動制御のスタンダードモデル
2.2 Adamsの閉ループ理論(closed-loop theory)とは
2.3 Schmidtのスキーマ理論(schema theory)とは
2.4 生態学的理論〜個体と環境の相互作用という視点
2.5 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント2 自由エネルギー原理に基づく運動制御と運動学習(濵田裕幸)
第3章 運動学習に関わる感覚運動的側面(林田一輝)
3.1 運動的側面から運動学習を考える
3.2 感覚的側面から運動学習を考える
3.3 身体意識と運動学習の接点を考える
3.4 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント3 有酸素運動と運動学習(松本侑也)
第4章 運動学習に影響を与える精神・心理的要因(川崎 翼)
4.1 動機づけは運動学習にどう影響するか
4.2 セルフマネジメントは運動学習にどう影響する
4.3 目標設定は運動学習にどう影響するか
4.4 自己効力感は運動学習にどう影響するか
4.5 認知機能は運動学習にどう影響するか
4.6 精神・心理的な変調は運動学習にどう影響するか
4.7 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント4 運動学習に関する文献の見つけ方と読み方(金 起徹)
第5章 運動学習の神経基盤(濵田裕幸)
5.1 運動学習の種類とその脳内機構を知る
5.2 運動学習の方略とその脳内機構を知る
5.3 運動学習過程によって脳内機構は変化する
5.4 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント5 運動学習研究のテーマの設定方法(鈴木博人)
インターバル “反復なき反復”〜運動学習の理解のためのさらなる視点(川崎 翼)
【第2部】運動学習を促進するための「課題設計と各種介入手法」
第6章 運動学習課題の設計と教示1:運動課題実施前(秋月千典)
6.1 課題の分割という視点:全体法と部分法
6.2 練習計画:練習の変動性と課題配置
6.3 課題設計時に考慮すべき変数
6.4 練習量と練習密度という視点
6.5 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント6 睡眠と運動学習(秋月千典)
第7章 運動学習課題の設計と教示2:運動課題実施中〜実施後(鈴木博人)
7.1 言語の利用という視点
7.2 注意の焦点化
7.3 フィードバック
7.4 能動運動と受動運動
7.5 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント7 運動イメージを利用した運動学習初期の学習効率向上に向けた一工夫(福本悠樹)
第8章 運動学習を促進する介入のエビデンス
8.1 課題指向型トレーニングによる介入のエビデンス(川崎 翼)
8.2 CI療法による介入のエビデンス(川崎 翼)
8.3 ロボット技術を用いた介入のエビデンス(林田一輝)
8.4 機能的電気刺激を用いた介入のエビデンス(秋月千典)
8.5 運動イメージや運動観察を用いた介入のエビデンス(福本悠樹)
8.6 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント8 運動イメージ戦略と運動学習効果(福本悠樹)
第9章 運動学習を促進しうる非侵襲的なニューロテクノロジー(濵田裕幸)
9.1 運動学習に寄与するニューロテクノロジー
9.2 非侵襲的脳刺激法(NIBS)によるニューロモジュレーション
9.3 非侵襲的磁気刺激によるニューロモジュレーション
9.4 非侵襲的電気刺激によるニューロモジュレーション
9.5 その他の非侵襲的手法によるニューロモジュレーション
9.6 テクノロジーを駆使したリハビリテーション
9.7 本章のまとめと取り組むべき課題
サプリメント9 運動学習課題の設定方法(川崎 翼)
【第3部】運動学習に関する知識を活かした神経リハビリテーション実践
第10章 運動学習に関する知識の活かし方
10.1 運動学習に関する知識の活かし方:総論(川崎 翼)
10.2 脳卒中者に対する運動学習の知識の活かし方の要点(松本侑也)
10.3 パーキンソン病者に対する運動学習の知識の活かし方の要点(金 起徹)
10.4 運動器疼痛者に対する運動学習の知識の活かし方の要点(金 起徹)
サプリメント10 発達・老化と運動学習(林田一輝)
第11章 運動学習に関する知識を活かした介入の実際─症例紹介─
11.1 脳卒中① 認知的介入により障害物跨ぎ動作の改善を認めた軽度脳卒中症例(松本侑也)
11.2 脳卒中② エラーレス学習を用いた介入により座位保持の安定性が向上した重度脳卒中症例(松本侑也)
11.3 パーキンソン病① 重心移動の運動学習〜外的焦点化を用いた感覚再重み付けの試み(金 起徹)
11.4 パーキンソン病② すくみ足に対する運動学習〜メンタルクロノメトリー評価に着目して(金 起徹)
11.5 運動器疾患① 人工膝関節全置換術後症例stiff knee gaitに対する歩容修正〜身体知覚異常に着目して(金 起徹)
11.6 運動器疾患② 集団リハビリへの移行によって運動恐怖感が軽減し、歩行・立ち上がりの速度が改善した慢性疼痛者(金 起徹)
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:20.1MB以上(インストール時:50.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:80.4MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:20.1MB以上(インストール時:50.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:80.4MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784763995766
- ページ数:320頁
- 書籍発行日:2025年5月
- 電子版発売日:2025年5月30日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍アプリが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。