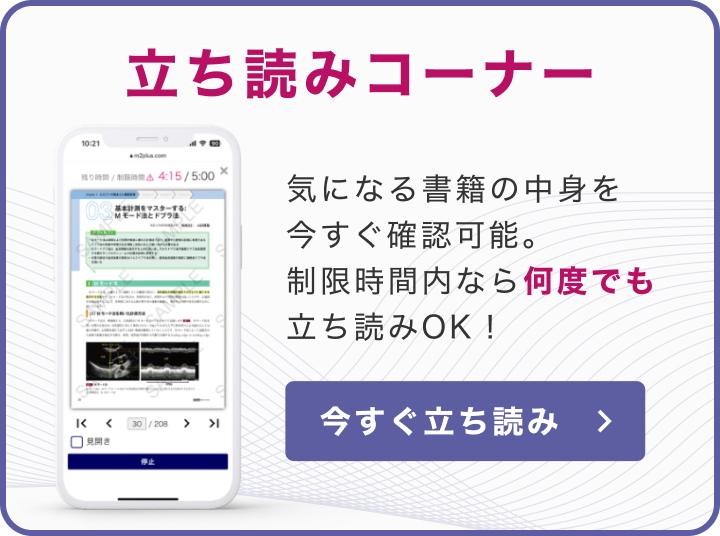- m3.com 電子書籍
- ねころんで読める不眠症
商品情報
内容
一般人口の約10% 、プライマリケア患者の約半数が不眠症を抱えていると言われている。不眠症治療において、国際的に第一選択となっている不眠の認知行動療法(CBT-I)を中心に、最新の薬物療法、合併症やライフステージに応じた治療についても解説する。
序文
推薦のことば
現在、世界では不眠症の治療において、睡眠薬に加え、不眠の認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia:CBT-I)と呼ばれる心理療法が高く評価されています。欧米では、この心理療法の効果が科学的に実証されており、不眠に悩む方に対して、専門家が最初にすすめる治療法(第一選択)とされています。こうした治療法は、欧米ではすでに標準的な方法として研究のトップランナーである医療現場で実践されています。
一方、日本では、欧米の研究成果を参考にし、国内で欧米諸国の研究成果をもとに新たな研究を行ってから導入するという手順が一般的だったため、普及までに大きなタイムラグが生じてきました。その結果、不眠症に対する心理療法は日本ではいまだ十分に定着しておらず、多くの方がやむを得ず、薬に頼り続けているのが現状です。
この状況を大きく変えようとしているのが、本書の著者・古川由己さんです。古川さんは、日々、患者さんと向き合いながら、不眠症に対する心理療法において、「何が本当に効果的なのか」を明らかにする研究に取り組み、世界的にも注目される成果をあげられました。日本発の研究が海外に発信され、科学的根拠として高く評価されているというこの流れは、これまで海外の後を追ってきた日本にとってタイムラグの解決をもたらす大きな転機となる出来事です。これは、眠れぬ夜に悩む当事者にとって新たな希望となり得るだけでなく、日本の睡眠医学や臨床心理学の研究者にとっても、非常に意義深いものとして受け止められています。
いま、世界的に最も注目される研究者のひとりである古川さんがまとめた本書では、こうした最先端の知見が、不眠に悩む方が日常生活の中で無理なく取り入れられるよう、丁寧に、わかりやすく紹介されています。そのわかりやすさの背景には、研究にとどまらず、患者さん一人ひとりの声に耳を傾けながら臨床と向き合ってきた古川さんの実践と人柄がにじみ出ているように感じられます。古川さんが、研究だけでなく臨床の現場でも積み重ねてきた経験と知識は、情報があふれる現代においても、安心して手に取ることのできる信頼ある選択肢として、本書の価値をいっそう高めています。
そうした確かな背景を持つ本書が、不眠で悩む方にとって、終わりの見えにくい長い夜を乗り越えるための新たな選択肢のひとつとなることを願ってやみません。一人でも多くの方が、本書を通じて安らかな夜を取り戻せますように。
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS) 特任准教授
(臨床心理士・公認心理師)
中島 俊
推薦のことば
あらゆる国において、あらゆる世代において、それぞれの科学分野には、その分野を代表するスポークスパーソンが必要です。特に、科学的に検証され、普及・実践が待たれる治療法がすでに存在する医学分野においてはなおのことです。私たちは、エビデンスに基づくCBT-Iの研究と臨床実践を生涯の使命として取り組んできましたが、日本における行動睡眠医学の分野では、古川由己医師がその役割を担うと考えています。
さらに重要なのは、ますます要求の厳しくなる医療の世界において、不眠症が多くの人々に影響を及ぼし、患者と医療システムの両方に大きな負担をもたらしている大きな課題であることです。古川由己医師の著書『ねころんで読める不眠症』は、まさにこの課題に応えてくれます。本書は、不眠症の診断と治療に関する充実した情報を提供しており、行動学的な視点と医学的な視点の両方を考慮に入れた包括的な内容となっています。さらに、ケーススタディが盛り込まれており、理論だけでなく、その実践的な応用が具体的に示されています。これらの症例は、読者にとって学習の機会となるだけでなく、どのような困難な状況においても、良い治療成果を得られる可能性があるという励みになります。
古川由己医師の優れた臨床的洞察力と、臨床研究者としての豊富な経験が、本書の確かな土台となっています。さらに、本書は、多くの治療マニュアルには見られない、日本の文化的背景を考慮した視点を備えている点も特筆すべきです。私たちは、本書の刊行を心から称賛するとともに、本書が日本におけるCBT-Iの普及を加速させ、多くの臨床家がこの治療法を提供できるようになることを願っています。
ペンシルベニア大学 精神医学 准教授/ペン行動睡眠医学部門 ディレクター
Michael Perlis, PhD, FSBSM
Sleepwell Consultants社長/スタンフォード大学 精神医学 臨床准教授
Donn Posner, PhD, CBSM, DBSM
序文
「最近、眠れないんです」
患者さんのこの一言を聞いたことがない医療従事者はいないでしょう。臨床現場に出るとすぐに、不眠を訴える患者さんに出会います。一般人口の約10%1)、プライマリ・ ケアの患者さんの約半数が不眠症を抱えている2)と言われています。
不眠でクリニックを受診すると、睡眠薬を処方されることが一般的です。しかし、薬では十分な効果が得られなかったり、患者さん自身が薬を望まなかったりする場合も少なくありません。臨床家としてはどうしたらよいでしょうか。睡眠衛生指導を試すこともあるかもしれません。しかし、すでに患者さんが自分で調べて試していることも少なくありません。飲酒や喫煙などの習慣に問題があっても、そんなに簡単にやめられるものでもありません。さて、どうしたものでしょうか。
私の専門である精神科では、睡眠薬を複数併用しても不眠症が改善せずに悩んでいる方がたくさんいます。私は睡眠薬以外の治療法を模索し、不眠の認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia:CBT-I)と出会いました。そして、CBT-Iの効果を目の当たりにしてきました。それもそのはず、世界の不眠症診療ガイドラインでは不眠症治療の第一選択はCBT-Iです3)。睡眠衛生指導は単体での有効性が示されておらず、米国睡眠医学会は非推奨としています4)。臨床試験でも、睡眠衛生指導よりもCBT-Iが有効であることが繰り返し示されています5)。睡眠薬のリスクを踏まえてCBT-Iが優先されているのかと思いきや、ランダム化比較試験のメタアナリシスで、CBT-Iが長期的にも短期的にも睡眠薬よりも有効であることが示されています6)。
長年不眠症で苦しんできた方が「先生、眠れました!」と晴れやかな顔で報告してくれるのは臨床家冥利に尽きます。CBT-Iと出会ってから、自分の治療選択肢に睡眠衛生指導と睡眠薬しかなかったときと比べて、格段に患者さんの不眠症が改善することが増え(もちろん全員ではありませんが)、不眠症治療が楽しくなりました。不眠症状を改善する特別な技法ももちろん役に立ちますが、患者さんの生活を具体的に理解しようとする姿勢も不眠治療以外にも役立つと感じています。
「でも、難しいんでしょう?」
いえ、CBT-Iはとてもシンプルです。
「でも、時間がかかるんでしょう?」
いえ、忙しい臨床現場で使える、実践的なものです。10分あれば導入できます。慣れてきたら、さらに小分けにしてさらに短時間にすることもできます。
「CBT-Iって、精神科医や心理士/心理師でないとできないのでしょう?」
いえ、プライマリ・ケアや看護の現場での実践例も多いです。不眠症で悩む方はとても多く、特定の科や特定の職種だけで対応できるものではありません。作業療法士や薬剤師による実践例もあります。効果が実証されているアプリも複数あります。
私は精神科単科病院や大学病院での入院だけでなく、クリニックの外来など、幅広い臨床現場でCBT-Iの実践を積みました。さらに、簡潔で有効なCBT-Iの提供を目指して、CBT-Iに含まれる複数の要素のうちどの要素が有効かを検討する研究を実施しました。論文はJAMA Psychiatryに掲載されました5)。本書では、これまでの実践と研究に基づいて、明日からの臨床で応用できるようにCBT-Iの実践法をお伝えします。
もちろん、現状では日本を含め、世界の不眠症治療の事実上の主役は睡眠薬です。第5章では、その睡眠薬について、臨床で用いられる主な薬剤の効果をレーダーチャートで視覚的に示し、また使い方のコツや注意点も詳しく記載しました。2025年5月現在、日本ではオレキシン受容体拮抗薬が3剤使えます。非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬にも、長期的な有効性が示されている薬剤があります。Lancetのネットワークメタアナリシスに基づいて、主要な睡眠薬が入眠困難や中途覚醒をどの程度改善するかもまとめました。また、睡眠薬は減薬・ 終薬において、特に注意が必要です。それについても詳しく解説してあります。
第6章では、多忙な外来診療でいかにCBT-Iを実施するか、入院環境でいかに実施するかについて述べます。また合併症やライフステージ、あるいは当直・夜勤といった就労環境ごとのエビデンスやCBT-Iの実施するうえでの工夫もまとめました。さらに第7章では、心理職、看護師、作業療法士や薬剤師としてCBT-Iを活用している事例を紹介しています。みなさんのかかわる不眠症治療が楽しくなることを祈っています。
2025年5月
東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻臨床精神医学教室
ミュンヘン工科大学医学部精神科・心理療法科
古川由己
1) Morin CM, Jarrin DC: Epidemiology of Insomnia: Prevalence, Course, Risk Factors, and Public Health Burden. Sleep Med Clin 17: 173-91, 2022
2) Bjorvatn B, et al: High prevalence of insomnia and hypnotic use in patients visiting their general practitioner. Fam Pract 34: 20-4, 2017
3) Qaseem A, et al: Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians.Management of Chronic Insomnia Disorder in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med 165: 125-33, 2016
4) Edinger JD, et al: Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults:an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med 17: 255-62, 2021
5) Furukawa Y, et al: Components and Delivery Formats of Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Insomnia in Adults: A Systematic Review and Component Network Meta-Analysis. JAMA Psychiatry 81: 357-65, 2024
6) Furukawa Y, et al: Initial treatment choices for long-term remission of chronic insomnia disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Psychiatry Clin Neurosci 78: 646-53,2024
目次
・推薦のことば
・序文
・患者さん・ご家族への注意事項/本書について
【第1章 不眠症って何?】
1 「眠れません」は不眠症とは限らない
TopIcs① 『君は放課後インソムニア』
2 慢性不眠症の治療は遷延因子に注目しよう
TopIcs② 『病草紙』
TopIcs③ 不眠に関する最古の記述
3 他の病気があっても不眠症の治療もしよう
【第2章 不眠症の治療法】
1 治療法の概説
2 不眠症治療のガイドラインとエビデンス
TopIcs④ 治療効果の大きさをどう理解するか
3 睡眠薬の適切な活用
【第3章 不眠の認知行動療法(CBT-I)】
1 不眠の認知行動療法(CBT-I)とは
2 睡眠日誌:日々の生活の様子をイメージする
3 臥床時間制限:臥床時間を短くすることで睡眠の質を改善する
TopIcs⑤ 起床時間を一定にする
症例1 仕事のストレスで眠れなくなった30代男性
4 刺激統制:寝床と睡眠を結びつける
TopIcs⑥ 日中の活動が少ない場合
5 認知再構成:不眠症を悪化させる思い込みを修正する
TopIcs⑦ 入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒ごとの使い分け①
TopIcs⑧ リラクセーションは逆効果!?
6 終結:CBT-Iで改善した場合、しなかった場合
TopIcs⑨ 対面CBT-IがデジタルCBT-Iより有効
TopIcs⑩ Q&A:認知行動療法は手続きが煩雑?
TopIcs⑪ Q&A:CBT-Iは実践や習得に時間がかかる?
TopIcs⑫ Q&A:CBT-Iは儲からない?
【第4章 睡眠衛生指導】
1 睡眠衛生指導とその歴史
2 睡眠衛生指導のエビデンスとガイドライン上の位置づけ
【第5章 薬物療法】
1 不眠症治療における薬物療法の位置づけ
TopIcs⑬ 「就寝前内服」「不眠時頓用」はいつ内服する?
2 長期的な有効性が示されている薬剤:レンボレキサント、エスゾピクロン
3 オレキシン受容体拮抗薬:レンボレキサント、スボレキサント、ダリドレキサント
4 メラトニン受容体作動薬:ラメルテオン
5 非ベンゾジアゼピン系:エスゾピクロン、ゾルピデム、ゾピクロン
6 ベンゾジアゼピン系
7 抗うつ薬(トラゾドン)、抗精神病薬(クエチアピン)、漢方薬の処方
TopIcs⑭ 入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒ごとの使い分け②
8 継続処方時/減薬・終了時
症例2 不眠症状に対して多剤併用となっている60代男性
【第6章 シチュエーション別CBT-I実践法】
1 外来10分診療で可能なCBT-Iの導入方法
2 入院環境でのCBT-Iの導入方法
症例3 うつ病で電気けいれん療法目的で入院した40代女性
3 合併症ごとのCBT-I
A アルコール使用障害/B 概日リズム睡眠障害/C 閉塞性睡眠時無呼吸症候群/D むずむず脚症候群/E うつ病/F 双極症/G 統合失調症/H PTSD(心的外傷後ストレス障害)/I 慢性疼痛/J 夜間頻尿/K がん/L 透析
4 ライフステージごとのCBT-I
A 中高生・大学生の不眠/B 高齢者の不眠/C 周産期/更年期の不眠(女性特有の不眠)
5 交代勤務(当直・夜勤)の不眠とCBT-I
【第7章 多職種からのアプローチ:Q&Aで理解するCBT-Iの実際】
0 多職種が行うCBT-Iの意義
1 心理職が行うCBT-I
坂田 昌嗣(公認心理師、臨床心理士)
2 看護師が行うCBT-I
根津 三千代(看護師/公認心理師)
3 作業療法士が行うCBT-I
佐藤 大介(作業療法士)
4 薬剤師が行うCBT-I
クオール薬局(クオールホールディングス株式会社)
【巻末資料】
1 不眠症の診断基準①:精神疾患の診断・統計マニュアル第5版改訂版(DSM-5-TR)
2 不眠症の診断基準②:睡眠障害国際分類第3版改訂版(ICSD-3-TR)
3 不眠症の診断基準③:国際疾病分類第11版(ICD-11)-Code 7A00
4 不眠重症度質問票(ISI)
5 睡眠に対する非機能的な信念と態度質問票(DBAS)
6 睡眠日誌
7 不眠症の診断・評価・治療まとめ
おすすめ参考図書
・あとがき
・索引
・著者紹介
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:52.4MB以上(インストール時:108.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:209.7MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:52.4MB以上(インストール時:108.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:209.7MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784840488235
- ページ数:216頁
- 書籍発行日:2025年7月
- 電子版発売日:2025年6月17日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍アプリが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。